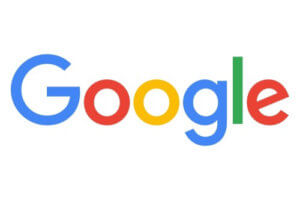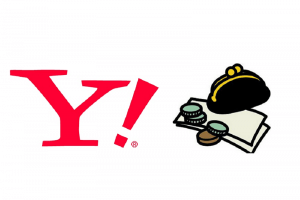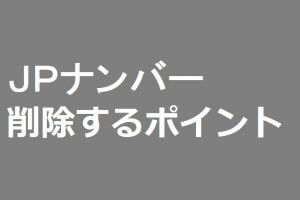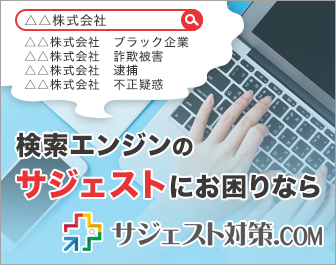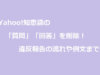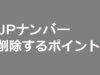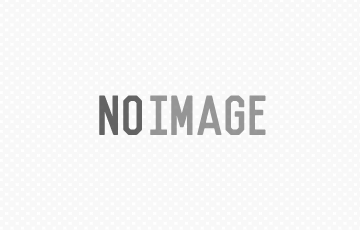インターネット リスクマネジメントは、いまや日本企業・自治体すべての経営課題です。日本IBMの最新レポートによれば、2024年におけるデータ侵害の世界平均コストが488万ドルと過去最高を更新しました。さらにIPAが公表した『情報セキュリティ10大脅威 2025』では、ランサム攻撃が10年連続で組織向け脅威の1位に選出され、サプライチェーン攻撃が2位につけるなど国内でも複雑化・深刻化が進んでいます。
警察庁の最新統計でも、2024年のフィッシング報告件数は171万8,036件、インターネットバンキング不正送金の被害額は約86億9,000万円と過去最大規模に達し、SNS型詐欺の被害額も前年比178%増の1,268億円に跳ね上がりました。こうした現実を前に、「何から手を付ければいいのか」「自社の体制は本当に十分か」と不安を抱える情報システム部門や経営層は少なくありません。
本記事では、日本の最新脅威動向を踏まえて「特定→評価→対策→監視」のフレームワークを整理し、初動対応チェックリストを含む10個のポイントを具体的に解説します。
インターネットにおけるリスクマネジメントの焦点

リスクマネジメントにおいて、まず注意しなければいけないのはどこに焦点を絞るかです。
それは、インターネットにおけるリスクマネジメントでも同様です。インターネット社会におけるリスクマネジメントのコツとしては、まず以下のポイントをおさえなくてはいけません。
風評被害・情報操作
炎上の主戦場はX(旧Twitter)、TikTok、Threads
2024年12月に国内で発生したネット炎上のうち、対象が企業・団体だったケースはおよそ90%。
批判の主体はサービス業だけでなくメーカー・自治体にも拡大しており、投稿量が平時比で急増する「波」が24時間以内に到達する傾向が強まっています。
AI生成コンテンツによる二次拡散
生成AIで作られた偽画像・フェイク動画が同時に出回ることで真偽確認が遅れ、一次発信よりも後から出た誤情報が検索結果上位に残存するケースが増加。社内外でのファクトチェック体制や、24時間モニタリングの導入が必須です。
個人情報・プライバシー
改正個人情報保護法(見直し案・2025年3月公表)
個人情報保護委員会は2025年3月、漏えい時の通知要件強化や国外移転の目的明示義務などを盛り込んだ改正案を公表しました。企業は「漏えい等報告 → 本人通知 → 公表」までの対応フローを事前に整備しておく必要があります。
報告義務と罰則の実効化
2022年施行の前回改正で罰則が最大1億円に引き上げられた経緯もあり、サイバー攻撃による漏えいはもちろん、目的外利用や同意の不備でも是正命令・公表リスクが生じます。EDR/DLPの導入だけでなく、取引先を含めたデータフローの棚卸しが急務です。
ブランドイメージ
採用・取引に直結するオンライン評判
2024年の調査では、内定辞退者の約20%が「ネット上のネガティブ情報」を理由に辞退したことが判明。新卒・中途ともに評価指標として「口コミ・SNSの評判」を重視する傾向が年々高まっています。
ステルスマーケティング規制(景表法告示)
2023年10月からは「広告であることの非表示」が景品表示法違反と明示され、違反企業には課徴金・社名公表リスクが発生します。インフルエンサー施策やUGC活用時は、#PR 表記・ガイドライン遵守を徹底し、炎上と法的リスクを同時に回避しましょう。
自社の現状を棚卸しし、ガバナンス整備・技術対策・広報対応をワンセットで見直すことが、2025年以降の競争力を左右します。
インターネットにおけるリスクマネジメントのポイント

以上のようにインターネットにおけるリスクマネジメントでは、風評被害、個人情報、ブランドイメージが3本柱になります。
それぞれ、具体的にどのような対策を講じるべきか、コツとなるポイントを紹介します。
風評被害の予防を徹底
インターネット上の風評被害はまず予防することが何よりも重要です。
ソーシャルメディア、ブログ、匿名掲示板などを網羅的に監視して、ネガティブな書き込みを早期に発見し、拡散される前に削除するように動かなければいけません。
削除依頼を申請した後も、確かに削除されたことを確認し、悪い噂が広まらないかどうか回復を見届ける必要があります。
インターネット上では「火のないところに煙が立つ」のは日常茶飯事なので、日々しっかりと把握していく体制を構築しなければいけません。
個人情報に関するフローチャートを作る
企業として個人情報をどのように取り扱うのか、スタッフ一人一人に周知させることがリスクマネジメントには欠かせません。
個人情報の取得、入力、送信、利用、加工、保管、バックアップ、消去などのすべてのフェーズでどう対応すべきかフローチャートを作成共有するようにしましょう。
ウイルス対策、IDやパスワードによるアクセス権限の設定、受け渡し記録、通信の暗号化・秘匿化、通信機器の物理的保守などにも注意してください。
ブランドイメージの重要性を再認識する
ブランドとは、企業の商品やサービスを差別化するためのネーミング、ロゴマーク、シンボル、パッケージ、デザインなどすべてを総括したものです。
それら一つ一つの重要性を再認識し、ブランドイメージをアップさせるにはどうするべきかつねに考えるようにしましょう。
インターネット上でのブランドイメージを考えると、消費者による投稿だけではなく、スタッフ・関係者の書き込みによって著しくブランドイメージを低下させてしまうリスクも少なからずあります。
ブランドイメージを保守するためにはヒューマンリスクをいかに管理するかということも非常に重要なのです。
リスクをシミュレーションする重要性

リスクマネジメントにおいては、どのようなリスクがあるのかシミュレーションすることも大事です。インターネット上のリスクに関するシミュレーションの有益性を高めるためのコツについて解説します。
他社の炎上例を参考にする
インターネットにおいては、悪評があっという間に流布されてしまういわゆる「炎上」のリスクをあらゆる企業が負っているといっても過言ではありません。
過去の炎上例を見てみると、ある一定の法則があることがわかります。
たとえば、モラルを疑うようなスタッフの悪ふざけを仲間内だけに見せる感覚で気軽に発信したような書き込みは、かなりの高確率で炎上するリスクがあります。消費者の書き込みを制限することは実質不可能ですが、せめて内部からの炎上は避けたいところでです。
スタッフのアカウントを把握する
ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアは、つい友達だけでやりとりしているような感覚に陥りがちですが、じつは全世界に向けて発信しています。
ラインでさえも、会話をスクショされてどこかにさらされる危険性はゼロではありません。
スタッフ一人一人にそういったリスクを周知させるとともに、できれば個人使用のアカウントも把握しておきましょう。ソーシャルメディアをする自由を奪うことはできませんが、スタッフそれぞれの個性を考えた上で、炎上リスクのある人を見守ることも大事です。
退職社員の動向に注意する
「ブラック企業だった」等、企業イメージを損なうような書き込みをする退職者は少なくありません。本当にブラック企業ならばそう書かれても仕方のないことです。
まずは、そのようなことを投稿されないよう、労使関係の健全性に関しては今後ますます注意しなければいけない時代に突入したと言えるでしょう。
しかし、企業の真の姿とは関係なく、人間関係のもつれからせめてネットで一言いわずにはいられない退職者もいます。できるだけ社内の人間県警にも心を配り、できるだけそのような退職者を出さないようにすることも大事です。
悪評を書くようなリスクがある退職者に関しては注視を行いたいところですが、プライバシーの問題もあります。投稿がありそうな場所をある程度シミュレーションして、日々見張ることも時には必要です。
リスクにとらわれすぎない
インターネット上には様々なリスクがありますが、逆に有益な情報もたくさんあります。
ビッグデータを活用すれば、消費者の動向をたえずチェックし、より良い商品作りやサービス提供に役立てるまでスピーディーに行うことができます。
リスクをシミュレーションするばかりではなく、新商品や新規サービスの提供をシミュレーションするにも役立てたいところです。
まとめ
以上のように、企業のインターネット上のリスクマネジメントは、どこに焦点をあて、どのように対応し、いかにシュミュレーションしていくかが非常に重要です。それにはまずインターネット上の関連情報を隈なく監視することがスタートラインです。
24時間365日体制で監視を続けるのは社内だけではなかなか難しいものがあるので、監視サービスを専門的に提供している会社などを利用することをおすすめします。一口に監視サービスといっても様々なタイプのものがあるので、くれぐれも信頼できる企業が提供しているサービスを利用するようにしましょう。