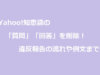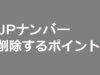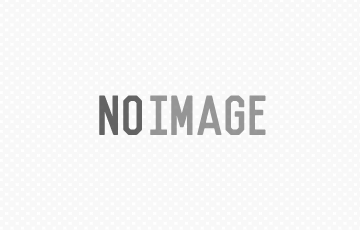「検索エンジンで自社名が検索されない…」
そんな悩み、ありませんか?
SNSや広告で認知を広げても、指名検索が増えなければSEO効果は限定的です。
実は“ブランド名での検索”は、検索エンジンにおける信頼性の証となり、間接的な上位表示にもつながります。
この記事では、検索エンジンにおける指名検索の意味とSEOへの影響、そして増やし方までわかりやすく解説します。
目次
検索エンジンにおける指名検索とは?
インターネットで何かを調べるとき、多くの人が最初に検索するのは「固有名詞」です。
たとえば、タレントやスポーツ選手、映画のタイトル、地名、テレビ番組、企業名などがよく検索されます。
また、「チケットぴあ」「Amazonプライム」「駅探」などのサービス名や、「終電なくしたんbyタクシー検索 たくる」のようなユニークなサービス名で検索する人も少なくありません。
このように、名前やブランドが特定されたキーワードで検索されることを「指名検索」といいます。
とくに企業にとっては、自社名やサービス名での検索結果がしっかりと上位表示されるかどうかが、信頼獲得の第一歩になります。
しかしせっかくWebサイトを作ったのに、自社名で検索しても検索結果の1ページ目に表示されない…。
そんな状態では、ユーザーの信頼を逃すだけでなく、大きなビジネスチャンスを失う可能性も。
指名検索でしっかり表示されることは、SEOの土台ともいえる重要なポイントなのです。
検索エンジンの指名検索対策をするメリット
検索エンジンにおける指名検索の対策には、下記のメリットがあります。
ターゲットとする顧客にリーチできる
指名検索する人の多くは商品や商材の購入を検討している段階です。
「製品を知りたい」「会社情報を知りたい」など明確な目的を持って検索しているユーザーを高確率で自社サイトに誘導することができます。
そのまま購入や資料問い合わせに繋げることができるでしょう。
流入数のアップを期待できる
指名検索で1ページ目に表示されると多くのユーザーの目にとまり流入数の増加が期待できます。
そこから新規顧客の開拓や獲得に繋げることができます。
検索アルゴリズムの影響を受けにくい
SEO対策が難しい理由の一つが不定期で実地される検索アルゴリズムの変動です。
アルゴリズムの変更により上位表示されていた記事がランク外になることは珍しくありません。
しかし、指名検索の場合は自社サイトとキーワードの関連性が高いためアルゴリズムの変動による影響を受けにくく上位を維持しやすい傾向にあります。
検索エンジンの指名検索や会社名検索で出てこない場合や検索結果が1位でなかったら?
検索結果がうまく表示(インデックス)されないのは何故でしょうか。
これにはいくつかのケースと原因が考えられます。
(ケース1)ノーインデックス(noindex)タグの外し忘れ
いちばん単純なのは、検索エンジンにインデックスされていないのかもしれません。その場合、サイト制作時に設置したノーインデックス・タグを外し忘れていないか確認する必要があります。
というのも、サイト制作時は検索エンジンにインデックスされないよう、ノーインデックス・タグを設置したままにすることがあるからです。
もしノーインデックス・タグがそのまま残っていた場合は、タグを外せばインデックスされるようになります。
(ケース2)会社名で検索しても評価が上がらない?原因はURLの表記ゆれかも
自社名で検索してもなかなか上位に表示されない…。
そんなときは、サイトのURLが複数パターンで存在していないかをチェックしてみてください。
たとえば以下のように、URLの一部が異なるだけで同じページが表示されるケースは要注意です。
- http://example.com
- https://example.com
- https://www.example.com
- https://example.com/index.html
このように、URLの先頭や末尾の表記がバラバラなまま放置していると、Googleの推奨する「URLの正規化(canonical化)」ルールに反してしまいます。
その結果、検索エンジンからの評価が分散され、サイト全体の順位が下がる原因になることも。
URLは一貫して統一し、正規URLを明示する設定(canonicalタグやリダイレクト)が、検索エンジンからの評価を高めるために重要です。
(ケース3)サイト名やページタイトルが英語表記のままだと検索されにくい?
サイト名やページタイトルに英語を使うこと自体に問題はありません。しかし、日本の企業であれば、ユーザーが日本語やカタカナで検索するケースが圧倒的に多いことを意識する必要があります。
たとえば、「SANYO Bookshop」という書店サイトを立ち上げたとしましょう。
この場合、多くのユーザーは「三洋書店」や「サンヨー」「三洋」などと日本語・カタカナで検索します。
しかし、サイト名やタイトルが英語表記だけだと、それらの検索キーワードでヒットしにくくなってしまうのです。
そのため、検索性を高めるには、次のように日本語やカタカナを加える工夫が必要です。
- サイト名例:「SANYO Bookshop サンヨー(三洋)書店」
- ページタイトル例:「Cooking Books(クッキングブックス)」
英語に不慣れなユーザーもいることを踏まえ、検索エンジンにも閲覧者にもわかりやすい表記を心がけましょう。
そうすることで、指名検索からのアクセスも増え、リピーターにも覚えてもらいやすくなります。
(ケース4)サイト内に検索キーワードに合ったコンテンツがない?
サイト名だけでなく、サイト内のコンテンツにも検索されやすい言葉を適切に含めることが、SEO対策では欠かせません。
とくに英語表記だけで構成されている場合、日本語での検索にヒットしづらくなるため注意が必要です。
たとえば、「〇〇〇football情報」というタイトルのページで、「サッカー」というキーワードでの上位表示を狙う場合を考えてみましょう。
ページ内やタイトルに「football」だけしか書かれていないと、多くの日本語ユーザーが使う「サッカー」という検索語に対応できません。
このようなケースでは、以下のような対策が有効です。
- ページタイトル例:「〇〇〇football情報(サッカー)」
- 本文内の例:「football(サッカー)の最新情報をお届けします」
検索エンジンに正しく内容を伝え、ユーザーにも親しみやすくするために、英語と日本語(カタカナ)を併記することが効果的です。
検索意図にマッチした表現を意識して、コンテンツを最適化していきましょう。
(ケース5)同名他社や紛らわしい表現が評価を下げる原因に?
自社のWebサイト内に、同名の他社や別業種の言葉が混在していないかを確認してみましょう。
たとえば、自社が「ハウスクリーニング(住宅清掃)」を行っているのに、サイト内に「カークリーニング」や「クリーニング店(衣類)」に関する表現が含まれていると、検索エンジンに誤った業種として認識される恐れがあります。
こうした混乱を避けるためには、サイトの内部最適化を行い、コンテンツの内容を明確に絞る必要があります。
特に指名検索においては、「この会社はどんな事業をしているのか」が伝わる構成が重要です。
さらに、検索エンジンやユーザーに「鮮度のあるサイト」と認識してもらうには、定期的なコンテンツの追加が効果的。
なぜなら、会社概要だけの静的なページでは、再訪してくれるユーザーも限られてしまうからです。
以下のようなコンテンツを継続的に発信して、サイトを強化していきましょう。
- 「〇〇〇のメリット」「〇〇〇の選び方」といったノウハウ記事
- 新製品やサービスの紹介、イベント告知
- 業界ニュースや社内ブログ形式のコラム
こうした更新により、サイトは検索エンジンからも高く評価され、ユーザーからも「また見に行きたい」と思われる存在になります。
また、他のサイトやメディアに自社の名前や情報を取り上げてもらう(=サイテーション)ことも、検索エンジン対策として効果的です。
たとえば、プレスリリースを活用して会社の新情報を他メディアに取り上げてもらうことで、信頼性や知名度が向上します。
特に地域密着型ビジネスでは、NAP情報(会社名・住所・電話番号)を正しく・統一して表記することもSEO対策として効果的。
検索エンジンは、こうした外部からの言及数や情報の整合性を重要視していると考えられています。
風評被害対策ラボでは内部最適化診断を行っております
これまで検索結果の上位ランク方法(SEO対策)についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。
風評被害対策ラボでは、風評被害対策だけではなく、サイトの内部最適化診断を、無料で個別に行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
またGoogleの推奨項目も変化します。
1年前と現在とでは優先すべき項目も変化しておりますので最新情報と実態を確認しながら施策を行うことをおすすめします。


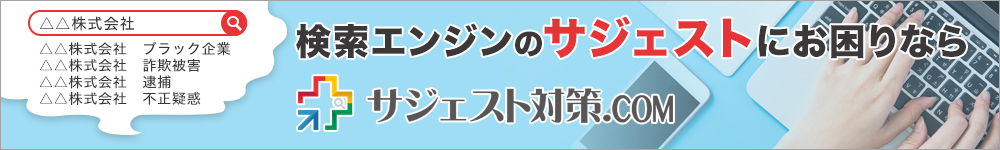






-300x200.jpg)